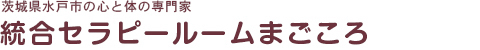あなたに起こる不安や恐怖とは?
私たちの誰もが対象のはっきりしない漠然とした「不安」や特定のものや状況に対する「恐怖」を感じたことがあると思います。
太古の昔から、人は不安や恐怖を感じた対象から身を離したり注意深く関わったりすることによって安全を確保し生き延びてきました。そういう意味では不安や恐怖そのものが「悪者」や「問題」であるわけじゃないんですね。
ただ、不安や恐怖が強すぎたり、ひんぱんに起こりすぎたりすると日常生活にも支障をきたすようになってしまいます。
ちなみに、日常生活を営むのが困難なほどに不安や恐怖が強く、さまざまな症状となって現われている状態を「不安障害」と呼び、正常な反応と区別して治療の対象としています。
また 「不安障害」は、症状の違いや症状が起きる状況の違いによって、いくつかに分類されています。例えば、凶悪犯罪を目の当たりにしたり、大きな天災がおこった後などに生じる可能性が高いのが「外傷後ストレス障害(PTSD)」といわれるものです。
これは、ショッキングなことを経験したり目にしたりすることで、その出来事が忘れられなくなり、そのことが何度も思い出され、そのたびに強い恐怖や不安・驚愕反応を起こすものです。他にも「パニック障害」「恐怖症」「強迫性障害」などがあります。
ここでは、そのような不安障害について、ご説明し適切な対応をお話していきますね。
【パニック障害】
■パニック障害ってなに?
パニック障害とは、「パニック発作」が繰り返し起こり、この発作がまた起きるのではないかという不安が常につきまとい、場合によっては、「パニック発作」 が突然起こっては困る場所(例えば、人ごみの中や電車、バスなど)を避ける行動を伴う「病気」のことです。
単なる「パニック発作」だけなら、パニック障害以外のからだの病気でも起こることがありますので治療の際には区別が必要です。
■パニック発作ってどんな状態になるの?
不安が身体的・精神的に急激に現れたものを「パニック発作」といいます。パニック発作では以下の症状が突然現れ10分以内でそれらの症状が頂点に達します。
・動機、または心拍数の増加 ・発汗 ・身震いまたは震え ・息切れ感または息苦しさ ・窒息感 ・胸痛または胸部不快感 ・嘔気または腹部の不快感 ・めまい感、ふらつく感じ、頭が軽くなる感じ、または気が遠くなる感じ ・非現実感、または自分が自分でない感じ ・コントロールを失うことや、または気が狂うことに対する恐怖 ・死ぬことに対する恐怖 ・感覚が麻痺したりうずいたりする感じ ・冷感または熱感 |
【恐怖症】
■恐怖症ってなに?
恐怖症とは、高いところやエレベーターなどといった状況や動物、血液などといった物事に対する恐怖や嫌悪感がかなり強く、さらにその感情が長続きしていて、日常生活になんらかの支障をきたしている状態のことをいいます。
また、このような必要以上の恐怖感や嫌悪感について、自分自身でも自覚していて、1日も早く開放されたいと感じています。
■どんな状態になるの?
恐怖症は、以下のような症状としてあらわれます。
・特定の状況または物事にさらされたとき、または、さらされるとわかったとき強い恐怖が現れ長く続く ・特定の状況または物事にさらされてパニック発作を起こす ・恐怖症である自分が客観的に見ておかしいと自覚している ・症状により生活に支障をきたしていたり著しい苦痛を感じていたりしている ・症状が少なくとも6ヵ月以上続いている |
恐怖症の対象となる状況や物事には、以下のようなものがあげられます。
状況 | ・嵐 ・高所 ・水 ・バス ・電車 ・トンネル ・エレベーター ・橋 ・飛行 ・自動車運転 (これが全てではありません) |
物事 | ・動物 ・虫 ・血液 ・注射 (これが全てではありません) |
【強迫障害】
■強迫性障害ってなに?
強迫性障害とは、ちょっとした不安や考え、感情などが頭にこびりついて「気にすまい」「考えまい」「行うまい」と努力するにもかかわらず、そうすればするほど、かえって心に強く迫り、それをやめると著しい不安が生じるため、そうせざるを得ない状態が続くことをいいます。
例えば、不潔への恐怖のため、電車のつり革や手すりなどは不潔でさわれないとか外出するとき戸締りしたかどうか気になって何度も点検しないと出かけられないなどがあります。
また強迫観念と強迫行為強迫性障害で現れるこだわりに対する観念を強迫観念といいこだわりに対する行為を強迫行為といいます。「強迫観念」とは、以下のようなことをあらわしています。
・頭の中に何度も繰りかえしでてくる思考や衝動またはイメージで、悪いことが起こるという強い不安や苦痛にかられる ・その悪い事がおこるというイメージは、生活の諸問題に対する不安ではない(現実に起こりうると思えないほど最悪の状態をイメージしている) ・その悪い事がおこるというイメージを解消しようといろいろあがいている ・自分自身の思い込みによるものだと自覚している |
また「強迫行為」とは、以下のような状態をあらわしています。
強迫行為は、強迫観念に駆られて繰り返しの行動を行います。例えば、手を洗う、順番に並べるなどをしたり、心の中の行為(祈る・心の中で言葉をくりかえすなど)をしたりする。そしてそれは、厳密に適用しなくてはならない規則があります。
つまり、これから起こるのではないかという事についての不安を取り除きたいためや、回避したいために行われます。しかし、この行動や心の中の行為は、それによって起こるであろう問題の緩和にはならないし過剰な行為です。
【外傷後ストレス障害(PTSD)】
■外傷後ストレス障害(PTSD)ってなに?
外傷後ストレス障害(以下PTSDという)とは、通常の生活ではおこらないような強い刺激(生命の危機など)を体験し、それが心の傷となり、恐怖・不安などの反応が繰り返しおこることをさします。
■PTSDの症状とは?
PTSDと診断されるには、以下のことが前提となります。
・自分が、危うく死ぬ、または重症をおうような出来事を体験したことがある ・生死に関わる場面を目撃したことがある PTSDの症状は、以下のような状態で、上記のような体験を何度も繰りかえし思い出します ・ただその出来事を思い出すだけでなく、その出来事が起こった際に見た映像や聞いた音、かいだ匂い、感触などを伴って思い出される ・夢となって何度もその出来事がでてくる ・その出来事が再び起こっているかのように感じたり、錯覚をおこしたりする ・その出来事を思い出させることに対して敏感に反応し、心理的な苦痛を感じる ・その出来事を思い出させることに対して敏感に反応し、身体的な症状(パニック発作やイライラ、集中力欠乏など)がおきる |
そのショッキングな出来事によってできた心の傷について、以下のような行為により常に回避するようになります。
・その傷と関連した、思考や感情を回避する ・その傷をイメージさせる行動や場所、人物を回避する ・その傷を思い出せないようにしてしまう ・大切な活動への関心や参加をやめる ・孤立している感覚 ・感情が豊かでなくなる ・未来に希望がもてないと感じる |
その他、以下のようなことも症状として併せもつことがあります。
・ 睡眠障害 ・怒りの爆発 ・集中困難 ・過度の警戒心 ・過度の驚愕 |
■不安障害の治療とは?
私たちの身体は、不安や恐怖を感じると胃の辺りがしめつけられる感じがし、心臓の鼓動や呼吸が速くなり、手に汗をかき、のどが渇くといった状態になります。このプロセス自体は、身体のメカニズムが正常に働いていることを表しています。
もしあなたが、このような心身の状態を体験したとしても具体的で理にかなった理由があるならば不安障害ではなく正常な反応であるということになります。
ですがもし、あなたに上に述べてきたような症状があって日常生活に支障をきたしているなら「不安障害」と呼ばれる治療を必要としている状態なのかもしれません。
その場合は、医師やセラピスト、カウンセラーなど専門家の助けを求めることが役立つでしょう。
「病院にいくほどではないかも?」
「なんとなく精神科に行くのは身構えてしまう…」
と躊躇してしまうなら、まずは気軽に行けるところに相談に行ってみてください。当セラピールームでも、不安障害ではないかという心配や病院へ行ったほうがいいかどうかという迷いについて相談することができます。
精神科、精神神経科、心療内科などを受診した場合、まずは診断がなされます。医師は、あなたの症状が不安障害によって生じているものなのか、他の身体疾患(例えば心臓疾患など)や精神疾患(例えばうつ病など)によるものなのかを鑑別し、あなたの状態にあった治療法ついて情報を提供してくれます。
もしあなたが不安障害と診断され病院での治療をうけることになると、その治療は大きく次の2種類になるでしょう。1つは薬物療法、もう1つは、カウンセリングです。薬は、症状をやわらげたり抑えたりするのを助けます。
服薬により、あなたは気持ちの上でも体力的にも余裕をとりもどし回復のプロセスを進めることができやすくなります。薬は、いわば急場をしのぐ松葉杖みたいなもんです。
私たちは、足をけがしたときに一時的に松葉杖に頼りますが、ケガが治ると同時に松葉杖はいらなくなりますよね。不安障害の治療における薬も松葉杖と似ています。一時的には薬に頼るような感じがするでしょうが、あなたの回復とともに薬は必要なくなります。
薬物療法を受けるときには、主治医とよく話し合って不安や疑問を解消してから服薬するとよいでしょう。
あなたの回復を手伝おうとしている医師なら薬についての質問にも丁寧に答えてくれるはずです。セラピーやカウンセリングでは「認知行動療法」と呼ばれる手法がとられることが多くなっています。
この方法では、あなたの「性格」や「おいたち」の中に原因を探ったり無意識に焦点を当てて分析しようとしたりはしません。
「認知行動療法」は、症状を具体的に把握し、症状に対するあなたのものの捉え方(認知)や行動を変えていくことによって症状に対処する能力を高め、最終的には薬を飲まなくても症状が出ない状態をめざしていくものです。
不安障害に限りませんが、私たちにとって心身の症状というのは、生活環境、生活のあり方(睡眠や食事、運動、仕事の仕方など)繰り返されている行動パターン、物ごとの捉え方、人生への態度・かまえについて、
“気づいたほうがいいことがあるよ”
“修正した方がいいことがあるよ”
と知らせてくれているサインです。その意味で、心身の症状を火災報知機の警報にたとえることができます。火災報知機の警報も“火災発生”を知らせてくれるサインだからです。
つまり火災報知機の警報は、ものすごくうるさいけど音が大きいからこそ多くの人がすぐに火災に気づくことができるんですね。
不安障害の中でも、パニック障害などは大変激しい症状を呈し、パニック発作の最中は死ぬかと思うほどの苦しみでしょうが、それほど強い症状を出せるということは、大きな音の警報を鳴らすことができる火災報知機にも似て回復に向かわせようとする身体の力が強いことを表してもいます。
火災報知機を叩き壊して「やれやれ、これで静かになった」と安心する人がいないように心身の症状を薬で押さえ込んで「なかったこと」にするのではなく症状が知らせようとしていたことに目を向けることが大切です。
自分の生活を窮屈なものにし、自分らしく生きることを妨げていたもの(例えば、生活環境やライフスタイル、物事のとらえ方、行動パターンなど)に気づいたならば少しずつでも変えていくといいと思います。
セラピーやカウンセリングは、特にこのプロセスにおいて有効です。
火災後の建物がひとりでに元通りになることはありませんが、私たちの身体は自然治癒力によって回復します。
一度火災を出した建物が、その後防災システムを強化することによって前よりも安全で快適な建物になるように、かつて症状に苦しんだ経験をもつ人、専門家と協力しあってそれを乗り越えた経験を持つ人は、不安障害になる前よりも自分らしく生きていけるのかもしれませんね。
お問合せはこちら
お問合せ・ご予約はこちら

お電話でのお問合せ・ご予約はこちら
029-303-6613
<営業時間>※完全予約制・不定休
平日:11:00〜19:00
土日祝祭日:11:00〜18:00